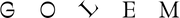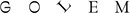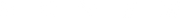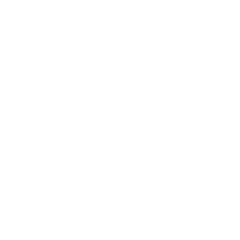クレイと同じ粘土鉱物を原料とした陶芸作品。
わたしたちGOLEMは、クレイ(粘土)を中心とした様々な天然素材を組み合わせケアするスキンケアを提案しています。陶芸作品もまた、粘土と様々な素材を組み合わせ作り上げるものです。一方は肌をケアするもの、一方は暮らしを彩るものとして使用されています。
今回素材コスメを混ぜ合わせるための器や、ディスプレイする際のプレートをお作りいただくため、わたしたちは岐阜県多治見市にある 故金あかりさんの工房までお邪魔させていただきました。

長い間シャッター街であった銀座商店街の店舗をリノベーションした工房は、昔ながらの温かみと、人が交わう新しさが融合する素敵な場所でした。この工房には、シェアハウスが併設されています。

-陶芸をはじめたきっかけを伺いました-
故金さん:元々デザインに興味があり、作ることが好きで、自分の手で形づくることのできる工芸をしたいと考えていました。様々な選択肢がある中で、粘土に触れた時にこれだ!と直感的に感じ、自分の感覚とマッチしたのが陶芸でした。
パナリ焼(沖縄県八重山諸島で19世紀中頃まで焼成されていたとされる素朴な土器)の展示にとても感化され、土自体の綺麗さ美しさと、物としてのおおらかさに魅了され、素材そのものについても考えるようになりました。


様々な素材の組み合わせから作り出される陶芸作品。
故金さんを代表する作品のひとつ、独自の化粧技法を用いた作品に魅了されたわたしたち。GOLEMのクレイを使用し器を彩るという初の試みを実験していただくこととなりました。
ニュージーランドで採掘されるグリーンクレイは鉄分をとても多く含んでいます。鉄は熱すると赤く色づくため、赤色を表現することができるのでは?と考えました。(あの有名な首里城も、沖縄のクレイである"クチャ"を使用して赤瓦を作っています)
こちらが実験の様子。
どの素材の組み合わせが一番適しているのかを検証します。
焼き上がりはこちら。そのままのクレイは鉄分が反応し、赤く発色しました。素材の組み合わせにより、器の色付けとして適したものへと変化します。パウダーの単味や水と混ぜた状態だと剥がれてしまうことが分かったので、今回は泥漿(でいしょう)と混ぜたもので彩色することになりました。
この実験結果を元に、器をお作りいただくことに。そして、その製作背景を今回特別に取材させていただきました。故金さん独自の技法で作られる作品は、とても細かな手しごとから生まれます。
粘土の塊を力強く練り込み、基盤となる粘土を形成。
そこからスライスし、粘土を裏表締めてから型へ。この型も、故金さんご自身が
石膏で作られたもの。
バーナーで炙るのは、型から取り出しやすくするため。取り出してからまたひとてま、焼成後のサイズを考慮し細かく測りながら口元部分の形をフリーハンドでカットしていきます。この工程を挟むことでニュアンスを生み出し、作品ひとつひとつに個性を持たせます。
さらに、色つけをするために最適な状態まで乾燥。この乾燥も乾かし過ぎず、ある程度水分のある状態にするよう、その時々の粘土の状態を見極めます。
様々な土を使い作品に色つけ。釉薬とは異なり、様々な素材である土を3色から5色程度重ねていきます。伝統的な日本の化粧技法を、故金さんが独自にアップデートした新しい技法。
今回はこの工程に、GOLEMのグリーンクレイを使用していただきました。
ここから更に乾燥させ、窯焼きの工程へ。
綿密に調整された温度で焼き上げていきます。温度が5度違うだけで、色も、雰囲気も全てが変わってしまうほど繊細。13時間かけて熱を徐々に上げながら焼き上げ、更に1日時間を置き、その翌日にやっと窯から取り出すことができます。


窯から作品を取り出します。まるで宝箱を開けるようにワクワクする瞬間。
焼き上がることで現れる、とても綺麗な色味。
そんな工程を経て、同じものは一つとない作品が出来上がります。
様々な素材を組み合わせ、作品を作り出す故金さん。
変化する自分に合わせて、素材を選びケアをするGOLEM。
異なる両者ですが、様々な共通点を見つけることができました。

故金あかり Akari Karugane
1995年岐阜県生まれ。2019年武蔵野美術大学工芸工業 デザイン学科卒業。2022年多治見市陶磁器意匠研究所ラボコース卒業。現在、岐阜県多治見市を拠点に作家活動を行い、国内外で作品を発表している。土の温かさと、おおらかさ、反対に繊細な表情を魅せられるような作品作りを意識。土の持つ要素と焼成による変化を活かしながら、器や壺、壁面作品へと落とし込む。
Instagram @karugane_akari
Photography by Tara Kawano
Written by Nana Kawabata
Supported by @moor_gallery @ikumihane